|
ジョナサンもこのことには動揺を隠せない様子だった。シャーマンでも騙される時があるのだなあ、と思った後に「当り前か。別に全能なわけではなし」と一人で呟いていた。 ボクは覚悟を決めた。今晩こそ、友達を見つける。そう意気込んで瞑想をし始めたのだが、興奮しすぎたのか、意識の集中がうまくいかなかい。焦りもあるようだ。二時間ほどトライしてみたのだが、足がしびれるだけで、時間がたつにつれ集中力が落ちてくるといった感じだった。 こんな時にこそ、ジョナサンは力を貸してくれればいいのに……と考えた後、人を当てにばかりしている自分が、恥ずかしくなった。 「ええーい、今日はやめだ!」と叫んで、床に寝転がった。その時、部屋の窓から星が見えた。きれいだ。キラキラしている。夜空を眺めるなんて久しぶりだなあ、と思いながら、しばらく星たちを眺めていた。ボクはなぜだかピノキオを思い出した。というよりも、あの映画にかかっていた曲を思い出していた。子どもの頃は、よくあの歌を歌っていたなあ。それから中学の頃、音楽の時間に偶然、太田先生が「私の好きな曲なの」と言ってあの曲――『星に願いを』を英語で歌ってくれた時、思いっきり感動して、母さんの財布をくすめてCDを買いに行ったっけ。そしてボクは一生懸命にあの歌を練習したんだ、英語で歌いたかったから――何度も、何度も……。 ボクはいつしか口ずさんでいた。 When you whish upon a star Makes no difference who you are Anything your heart desires Will come to you お星様に願い事をすれば、 君が誰であろうと、 本当に心から願っていることなら、 叶えてくれるよ。 英語の成績はぜんぜん上がらなかったけど、ボクもボクなりに一生懸命、英語を勉強していた頃があったんだなあ……。 そして、ボクは無意識のうちに呟いていた。 「お星様、ボクは友だちを見つけたいんだ」 いつしか眠りについていた。 ボクは森の中にいた。 カラスが一羽、闇の中を飛んでいる。 まただ。子どもの頃からよく見る夢だ。いつも捕まえられなくて、どうせ、どうせまた、目が醒めるんだ。ボクは半分寝ていて半分は起きているというような状態だった。 どうしてもあのカラスを捕まえなければ……。でも、どうせまた無理なんだろうな、と思った瞬間、遠くの空から、真っ白なものが飛んできた。目が光っているような気がする。鳥だ。あの鳥だったら、ボクが子どもの頃から追っていたカラスを捕まえることが出来るかも知れない。 その白い鳥は、ボクを見つけるやいなや、すごいスピードでボクの方に飛んできた。それは、フクロウだった。そして、目の前で羽をばたばたとさせると、ボクの右肩にとまった。彼はボクに言った。「冒険に出る気になったんだね」 こうしてボクは、友達を見つけることが出来たのだ。 そのことを次の日の朝、ボクはジョナサンに語った。 「そいつは良かった。これで君も彩香に逢いに行けるというわけだ」 ジョナサンはフライパンの目玉焼きをひっくり返した。 「ウン。でもフクロウがボクの友だちだなんて、正直言ってびっくりしたよ。ボクは人間が出てくると思っていたから」 ボクはグラスにオレンジジュースを注ぐ。 「人間の友達が出てくる時もあるよ。だが、たいていの場合は動物のほうが多いのだよ。ちなみに私の友だちは、ネズミだ」 「ネズミい! ジョナサンの体型とえらい違いだ」 「あはは、そうだね。ところで彼には名前をつけてあげたかい?」 「名前? そういやつけていないや」 ジュースのパックを、ボクは冷蔵庫にしまいこむ。 「つけてあげないと。だが名前をつける前に彼が自分でつけたい名前があるか訊いてあげないとダメだよ。彼の意志を尊重するんだ」 目玉焼きが、お皿の上にのった。 「ウン、判った。後で瞑想した時にそうする」 といった具合に、ボクはすっかりシャーマン的な会話を違和感無くしていた。 考えてみると不思議なものなのだが、自分が一度そういう経験をしてみれば、いままでウソや戯言だと思っていたことが、受け入れられるものなのだ。もっともジョナサンに言わせれば、ボクはけっこう疑い深いところがあるわりには単純なところもあるそうなので、もっと自分の中にある力の存在を信じるようにすれば、今よりスンナリと彼の教えを吸収できるらしい。 「いいかい、次の四番目の鍵は、友だちのフクロウ君から直接受け取ることになるが、君はここでかなりいやな目にあうかも知れないことだけは言っておく」 フォークをボクに渡した。 「彩香にはすぐ逢えないの?」 ボクは、サラダにドレッシングをかける。 「君次第だ」 ウィンク。 「いただきます!」 二人そろって、手を合わせて言った。 朝食を終え二時間ほどたってから、ボクはマンションの裏山で瞑想に入った。フクロウの友だちには、予めここで瞑想をやると言っておいたので、彼はスンナリとボクのヴィジョンに現れた。飛んでくるとボクの右肩にとまった。 「やあ」とボクは挨拶した。 「やあ、元気かい。調子はどうだい?」 「うん、まあまあってところかな。そうそう、ジョナサンが、君に名前をつけてあげなって言ってたよ。何か希望の名前はある?」 「君がつけてくれ。しっくりとくるやつにしてくれよ。それから、気を使ってくれたジョナサンにぼくからよろしく、と伝えておいてくれ」 「うん判った。名前のことなんだけど、セルジオってのはどうかな? 実は予め考えておいたんだ」 「知ってたさ。セルジオ――君が昔よく聴いていたジャズ・ピアニストと同じ名前だね。うん、気に入った。セルジオって呼んでくれ」 昔よく聴いていたジャズ・ピアニストと彼に言われるまで、すっかりセルジオ・サルヴァトーレのことは忘れていた。彼のほうがボクの過去に詳しいっていうのも何だか変な感じだ――と思った瞬間に「だって、ぼくは君自身でもあるからね」と言われた。何となく判る気がしたので、ボクは頷いた。「四番目の鍵についてなんだけど……」 「うん、判っている。ジョナサンから何かヒントはもらったかい?」 「ジョナサンは、かなりいやな目に逢うかも知れないって、言ってた」 「じゃあ、いやな目に逢わせてあげよう――っていうのは冗談。四番目の鍵は、じつは今まで君がジョナサンから教わってきたことが中心になっているので、彼はボクから教われって言ったんだ。『内心と外心とこの世界の繋がり』とでもタイトルをつけておこうか。現在、過去、未来、霊在の意識の話はジョナサンから聞いたよね?」 「うん」 「その先のことを説明すると、それぞれの意識には内心と外心というのがあって、この二つは各々働きが違うことから便宜上分けているだけで実際は……」 「別々なものではない――だろ?」 「そう。内心とか外心とか呼び名は違うけど二つでひとつ――二個いち――と今は考えておいて問題はない。つまり、君の現在意識は君の外心と内心で構成されているんだ。代表的な働きとしては、君が何か外から刺激を受けたとする。それを受けたのは外心で、そこから内心に情報が伝わる。そして内心は反応を起こして外心にそれを伝え、君は何らかの行動をとる――というのが一連の働きなんだけど……」 「ちょ、ちょっと待ってくれ。セルジオ、難しいよ。何か具体的な例をあげてくれ」 「ごめん。先を急ぎすぎたね。例えば、君が今朝食べたサラダの中にあったレタス。あれを口にした時、きみはどう思った?」 「感謝しながら食べようとはしているんだけれど……」 「言い訳はいいから!」 「正直に言うと、まずい、と思った。ボクは子どもの頃からレタスが嫌いなんだ」 「うん。君がレタスを食べておいしくないと思ったのを例にすると、君がレタスを口の中に入れたというのが刺激。その刺激を受けて内心に伝えたのが外心。まずいと反応を起こしたのが内心。その反応が外心に伝わって君の目は少し涙ぐむという結果反応が生じた。刺激→外心→内心→外心→結果反応――これが基本だ」 セルジオはバサっと飛んで、近くの木の枝にとまる。瞑想中、いつの間にかボクたちは森のイメージの中にいた。 「つまり、まずいと思っているのは内心だ、ってことだね」 「なかなか飲み込みがいいじゃないか。それでは、なぜレタスを食べた時に、君は“まずい”と思ったのだろう?」 「それは……ボクがレタスがきらいだからだ」 「う〜ん、それも答えだけど、きらいな理由は?」 「レタスは、何となく、にがいからなあ」 「あとは?」 「そうだなあ、実はあの色もなんだか苦手なんだ――うすーい緑」 「黄緑だね。まあそれぐらいで良いか。今君が言った理由が、実は内心の中でこんな具合に形成されているんだ」 と言って、セルジオはくちばしで、地面にこんな図を描いた。 |
||
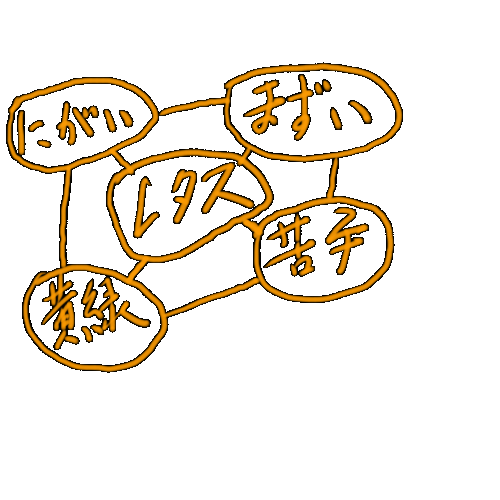 |
||
| 「他にももっと繋がっているんだけど、こういった訳で “レタス=まずい”という反応を外心に返してきて、君はレタスをまずいと答えた。結果としてでてきた反応で涙ぐんだのは感覚器官が“にがい”あたりに繋がっているんだろうね」 「ねえセルジオ、この図でいくと“黄緑=まずい”も繋がっているってことだろう?」 「そうさ」 「“黄緑”が“まずい”なんて、ボクはそんな反応はしないと思うよ。ちょっと変だぜ、この図は」 「いや、今は完全にこの図が理解できていないからそう思うだけであって、これでいいんだ。そのうちおいおい説明していくよ」 「セルジオが話している時、前にジョナサンとポジティブな面に目を向ける話をしたのを思い出したよ」 「うん。それも関係している。ポジティブな面に目を向けるのは、外心の働きにあたるんだ。君はレタスをまずいと思っているよね。そのレタスについてなにかポジティブなことを考えてみて」 「ポジティブと言われても、まずいものはまずいんだから、考えようがないよ」 「何でもいいから、無理やりにでも」 「んー。じゃあ、とりあえず、レタスは野菜だから“体に良い”ってのは?」 「それでいこう。ポジティブな面に目を向けると、さっきの図は一時的にこうなる」 |
||
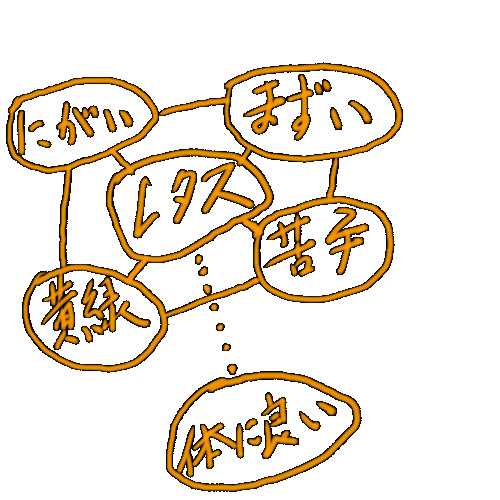 |
||
レタスは体に良い。その外心の働きがあった場合の反応は、レタスを食べる(刺激)→それは体に良い(外心)→まずい(内心)→まずいけど体に良い(外心)→やっぱり少し涙ぐむ(反応結果)になる」 「結局、涙ぐむのは変わらないんだァ。まずいものはまずい」 「あはは、涙ぐむという結果だけを見れば一緒だけど、ここで重要なのは刺激を受けた内心から外心への反応なんだ。『まずい』と反応を返すのと『まずいけど体に良い』と返すのとでは、君を含めた意識全体に及ぼす影響に違いが出てくるんだ。そしてそれは現在、過去、未来それに霊在意識へと影響しているんだ」 「レタスをまずいと思って食べることが、現在、過去、未来、それに霊在にも影響をあたえるの? たったそれだけのことが……」 「影響はそんなに大きくないけどね。微妙だけど絶えず意識同士は影響を及ぼしあっている。すべては繋がっているとジョナサンから聞いただろう?」 「聞いたけど、それは動物や植物や大地とであって……」 「違うよ。動物とか植物とか分け隔てるから判らなくなっちゃうんだ。すべてが意識をもっているんだ。いや、この言い方も変だなあ。そうだ、大きな意識の中に君の意識や、ウサギや牛や、ひまわりたちの意識がある。自然という大きな大集合の中に個々の部分集合がある、というふうにイメージしてごらん。そしてこの大自然という素敵な環境を提供してくれている地球は銀河系という大きな大集合の中にあって、銀河系はそれよりも大きな大きな宇宙という大集合の中にあって、という具合にイメージしてごらん。それから本来それらはもともと分け隔てなんかないのだと」 ボクは目を見開いた。「そう考えると、ボクイコール大きな大きな宇宙ってことになってしまう」 「そうさ」 平然とセルジオは答えた。 「そうなの?」 「そうさ。それに現在意識も過去意識も未来意識も霊在意識もがその中にあるんだ。そういうふうにイメージしてごらん」 ボクはセルジオとの会話を一旦中断し、イメージ化につとめた。それから「君の言った通りイメージしてみると、結局ボクってすごい意識になっちゃったよ」と、冗談めかして言った。 「そうさ、君は本来スゴイんだ。大きな大きな宇宙のことを想像できる力を持っているのだからね。君の心っていうのは、それぐらいだだっ広いんだ」とセルジオはウィンクした。「話を戻そう。今度は君がサラリーマンになるまえによく読んでいた願望実現関係の本についての例え」 「えっ、あれかあ。あれは効かないよ。何度か試してみたけどぜんぜんダメだったよ。一瞬信じたボクがバカだった。でもどうしてその話を例にするの」 セルジオが言い出すまですっかりあんな本のことは忘れていた。もう十年近くも昔のことだ。 「その話が一番おもしろいかな、と思ったからさ。あの方法は効かなかったんじゃない。君が間違って実践していたから効かなかったように思えただけで、実際は効いていたんだ」 「どういうことだい? ボクはあの頃はいつもミュージシャンになりたいって思っていた。あの本には、実際それになったという姿をありありと映像化していればなれる――みたいなことが書いてあった。だから、ボクは卒業して会社に勤めだしても毎日毎日その映像化に励んだんだ。朝、昼、晩と一回につき十分ぐらいづつ。でも、ボクはミュージシャンにはなれなかった。そういえば、その本にも宇宙の法則とか、ちんけな内容が書かれていたっけ」 「そのちんけな法則はちゃんと機能していたんだよ。今も機能している――君の意識の中では、ちんけなものとして。いいかい、あの映像化するテクニックとは、意識をそのなりたいものに合わせることなんだ。一番大切なことはどれだけ感情が伴えるかってことなんだけど――そうすると意識のスポットが合って拡張するからね。 きみはあの頃、朝、昼、晩は一生懸命、なりたい姿を映像化していた。それは認めるし、たしかに朝、昼、晩の十分間はすべての意識にその影響を与えていた。でも、それ以外の時間は、どうだった? 会社で仕事をしている時や、家に帰ってからテレビのお笑い番組を見ていたときの君の意識状態は?」 「――?」 「きっと会社では、君はサラリーマンとしての意識状態で仕事をこなし、家に帰ってもサラリーマンの意識でテレビを見て、ご飯を食べ、お風呂に入って、寝る前には『ああ明日も仕事かあ。金曜日まではまだまだだなあ』といったサラリーマンの意識で過ごしていただろう?」 「それなら、一日中映像化していろとでも言うのかい? 出来ないよ、そんなこと」 「ちがうちがう。一日中その意識のスポットから行動しなさいってことだよ。考えたり映像化するということと意識状態を保つというのをゴチャ混ぜにしちゃダメだよ。変な言い方になるけど、意識のスポットをミュージシャンの位置に固定して、その意識のスポットで仕事をこなし、テレビを見て、ご飯を食べ、お風呂に入ればよかったんだ。でもあの時の君は、一日のうち朝昼晩の三十分以外――残りの二十三時間三十分――の意識のスポットは、サラリーマンであったり、たくさんの美女に囲まれたハーレムのような生活を夢見たりってな感じだった。挙句の果てに君は、もし本当にミュージシャンになっちゃったら売れなくなった時の生活はどうしようか、と変な心配までしていた――未来に対する取り越し苦労だ」 ずいぶんと痛いところをついてくるけど、確かにセルジオの言う通りだ。もっとちなみに、学校を卒業する頃は一方では「ミュージシャンになりたい」とう願望がありながら、もう一方では「早く会社を決めなければ」という思いもあった。振り返って見直してみると、いい加減な意識状態だったものだ。 「だから結論としては、君が普段何気なく感じていることや、思っていること話していること、それにやっていることのほうが大事だったんだよ。意識は一分一秒も休むことなく影響しあっているんだから。そういった日常生活の意識がミュージシャン的な意識状態を保っていれば、周りの意識を誘発して、君はミュージシャンになっていた。君たちの世界で言う、そういう現実を作り上げていた。だけど実際は『ああ明日も仕事かあ、金曜日まではまだまだだなあ』という現実が出来上がっていた。だって意識がそうだったのだもの。内心と外心で説明すると朝昼晩トータルの三十分は、 ミュージシャンになった(外心)→ボクはミュージシャン(内心)→ボクはミュージシャン(外心)→ミュージシャン(反応結果)と内心からの外心の反応が『ボクはミュージシャン』という具合になっているから現在意識のスポットがそこに合わせられる。そこにバンド活動なりの意識的行動が加わりスポットされていれば、君はめでたくミュージシャンだ。 今度は残りの二十三時間三十分について。 ミュージシャンになりたい・定職につかなければ(外心)→???(内心)→ミュージシャンになりたい・定職につかなければ+???(外心)→ミュージシャンになりたい・定職につかなければ+???(反応結果)。行動の方はというと仕事を探したり、時々趣味程度でギターを弾いてみたりと行動のスポットもバラバラだ。何の結果も生まれない」 「それじゃあセルジオはあの本にウソはなかったというんだね。願いは何でも叶うんだね?」 「今みたいな例に関して言えばイエス――と言いたいところなんだけど、実はこれにはある条件が満たされていることが必要なんだ」 「条件が満たされている?」 「そう。それが内心にあるんだ。きみはあの頃、ミュージシャンになることに対してどんなイメージを持っていた?」 「そうだな、カッコ良い、おカネが儲かる、モテる、自由、ってところかなあ」 「また随分とミーハーなイメージばかりで……」セルジオは羽根でこめかみを掴んで首を振った。「それだけかい? 何か否定的な考えとかはなかった?」 「うーん、生活が不安定そうなことかなァ」 「じゃあ、その条件で図を描いてみるよ」 |
||
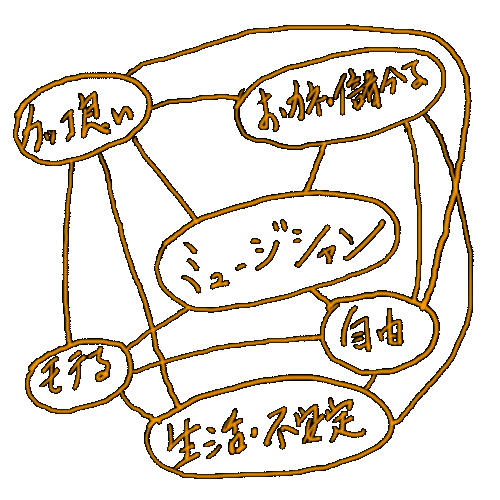 |
||
| 「おカネが儲かることやカッコ良いことが不安定エ?」 思わず声が裏返った。。 「まあまあ。まだ終わってないんだ。次に不安定からどんなことを君は想像する?」 「危険……かなあ」 「危険なことといえば?」 「高所作業。なんだか怖そうだ」 それを聞くと、セルジオのくちばしはマシンガンのような勢いで、また地面に図を描き始めた。 |
||
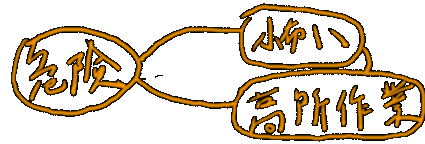 |
||
| 「あっ、そうそう。変なこと訊くけど、君はカネ持ちのことをどう思っている?」 セルジオが何でこんなことを急に訊くのか不思議に思ったが、思っているままにボクは「なんか、汚いことやって儲けやがってというイメージがあるから、きらいだな」と答えた。 「ふーん。じゃあヤクザは?」 「ヤクザは怖いよ。悪いやつらとは、あまりかかわりたくない」 「なるほど。総合するとこうなる」 |
||
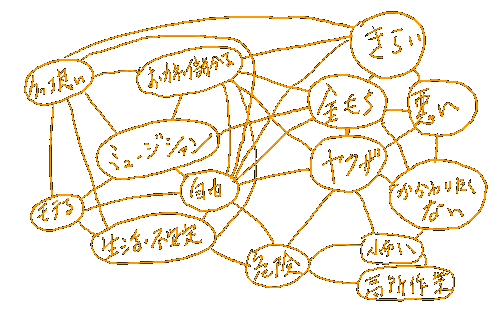 |
||
| 途中まで描いて、セルジオは大きくため息をつくと「とてもじゃないけど全部の線を結ぶことは簡単にはいかない」と言い、ボクの方を見て「抜けているところもあるけど、まあ、こんな感じだろう」と両肩を上げた。 「これらが全部繋がっていると言いたいんだね」 「そう。君の内心ではね。このネットワークが願望実現を邪魔している時があるんだ。だから、映像化したり行動しても、物事がうまくいかないことがあるんだ。それが内心の相殺なんだ」 「ソウサイ?」 「そう、相い殺す。この図を見て、君がプラスだと思うこととマイナスだと思うことに分けてみて」 ボクはプラスのほうに、カッコ良い、モテる、おカネ・儲かる、自由、をあげた。そしてマイナスの方には、生活・不安定、きらい、怖い、悪い、危険、かかわりたくない、をあげた。ミュージシャンやヤクザ、カネ持ち、高所作業は分けられないような気がしたのではぶいた。 プラスの個数が五個。マイナスの個数が七個あった。 「五つの要素が相殺されて、残りの二つの要素は――項目は何だか判らないけど――マイナスだ。この二つの要素が、君が分けられないと言ったミュージシャン、ヤクザ、カネ持ち、高所作業といった事柄に影響を与えているんだ」 「つまり、相対的に見るとマイナスの要素が多いから、その事柄に関しては、マイナス的な現実が発生しやすいってことかい?」 セルジオは頷いた。 「内心の中はもっと大きなネットワークが形成されているんだけど、意識のスポットはだいたい図の通り」 「じゃあ、プラス的な要素のネットワークを作っておけば、プラス的なことが多く発生するってことだね」 「そう。そのために物事をポジティブな面から見なさい、とか日常生活や、言葉に気をつけなさいとジョナサンは言うんだ。それはネットワークの再構築化を行い意識のスポットをプラスのほうにあてるためなんだ。要は現在意識がどこにスポットをあてているかと言うことなんだ。意識というのは考えていることだけを言うのではなく、思考・感情・行動だよ」 「思考・感情・行動、日常生活に言葉使いに霊在意識と現在・過去・未来――ややこしいなあ、いっぱいありすぎて。覚えきれないよ」 「言葉で考えるとややこしくなる。それに別に覚える必要なんてない。この先このことをもっと深く理解していきたいのなら日常生活をもっと意識的にすることだ」 「ボクは、もっと瞑想することだ、とセルジオは言うと思った」 「いや、ジョナサンみたいに日常生活が意識的になっていれば、瞑想も有益なものになってくるけど、君の場合は日常生活を意識するという瞑想のほうが大事だ」 「日常生活が瞑想なの?」 「そうさ。オレンジジュースを飲んでいる時も、本を読んでいる時や何かを話す時も、どんな時でも瞑想はできる。いつでも瞑想状態でいられること――それが瞑想の目的のひとつなんだ」 「なんだか難しそうだなァ」 「難しそうだなァ――という意識のスポットが今あちこちの意識に影響を与えて、君の現在意識が日常生活での瞑想を難しそうなものにしているよ」 「あっ、ごめん。今のが言葉による影響になるんだね? でも、瞑想しているからこそ君ともこうやって会話が出来るのだし、やっぱり瞑想も必要なものだろう?」 「そうだよ。瞑想と日常生活を分けて考えるからそんな考えになってしまうんだ。瞑想を生活の一部にしてしまえばいいんだ」 「なんとなく判ったよ」 「なんとなく?」 「ごめん、もうすぐ完全に理解できるよ」 「うん。長たらしいけど、その方がいい表現だ」 その後、ボクはセルジオからネットワーク探しの方法を詳しく教わり、瞑想を終えた。 静かに目を開け時計に目をやると、三十分程しか時間は経っていない。 おもむろに、胸元のポケットから携帯を取り出して見た。バッテリー表示がゼロに近い。家に帰って充電をしておかなければ、と思った時、カサッという落ち葉を踏みつける音がした。 誰かいる――と、直感。そして、その誰かが誰なのかも、すぐに判った。が、足に痺れが入っているので、すぐには立ち上がれない。 どうする? しばらくはこのままの姿勢でいるか。 落ちついて、ボクは口を開く。「メルスだろう」 ハッタリで言うと「そうだ」と木陰から声をだし、彼は正面から姿を現した。彼の後ろには大柄の男が三人いる。 なんだ、日本語が判るんじゃないか。 ボクは、ゆっくりと趺座をといて、周りを見た。 左・右、後ろの茂みに、ひとりずつ――合計七人か。 「全員そろって黒のスーツとは、また趣味のええこってエ」 関西弁で余裕のあるふりをした。変に度胸がある自分に驚いた。 「我々と一緒に来てもらおう」 とメルスが言うと同時に、取り巻きたちが銃を構えた。 「どないする気や?」 「我々の開発した新薬で、君の意識の強制拡張を行う」 メルスは、スーツの胸元から薬のビンを取り出した。 セルジオ―― 心の中で、ボクは彼を呼んだ。 (君の肩にいるよ) (どうしたら良いと思う?) (逃げるのが一番ベストだと思う) (当り前な答えだな。ボクは逃げるのに何か良い方法はないか、と訊いているんだ) (足の痺れがとれるまで、とりあえず時間稼ぎをする) (言えてる) 痺れている方の指をゆっくりと動かしながら言った。「ヤハウェの発音を知るためにやな」 メルスは二三歩前進した。「心配することはない。薬を飲めば、楽に言葉に焦点を合わせることができる――思い出せる、ということだ。少々副作用はあるがな」 「そんなヤバい薬を、ボクに飲ませんのかァ?」 彼らは徐々に距離を狭めてきた。 (大丈夫、完全じゃないけど走れると思う。どうやって逃げれば良い?) (自分で考えな) (冷たいゾ、セルジオ!) メルスに握られた薬のビンの蓋が開いた。 周りの連中が取り押さえようとした刹那、ボクは半ば投げやりで、勢いよく屈伸して後ろの奴のアゴに頭突きを食らわした。 振り返り、倒れた奴の顔を踏みつけ、ダッシュ。 それから、茂みに飛び込み一回転。 立ち上がり、再び駆け出す。 パンパーンと後ろから銃声がした。 怒鳴り声が聞こえた。たぶん「撃つな」と言ったのだろう。撃ち殺されることはない、と判断したとたん、ある程度の余裕を感じた。 降り口とは反対方向に駆けたので、山を登っていることに、途中で気づいた。 この木々を越えたら方向を変えよう。 だが、そう思った瞬間に体の力がいっきに抜け落ち、バランスを崩す。 視野が、激しくぐらつく。 崖だ。 「うわっ」 地面が見える。 「――!」 ダメだ――と、感じた時、一瞬にして目の前が真っ白になって、すべての感覚が消えた。 ボクは死ぬのだ、このロサンゼルスの地で。 |
||